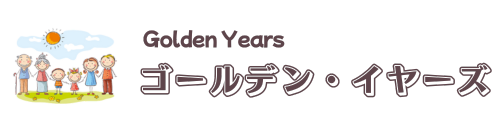ゴールデン・イヤーズ?
What is Golden YEARS ?
ゴールデン・イヤーズ(Golden Years)とは、当社ニアノーチェストが運営する会員制サービス事業の総称です。
千葉県松戸市を拠点とし地域密着型の参加体験型プログラムを会員の皆さまや参加される皆さまに対しサービスとして提供しています。




「シルバーから“世界基準であるゴールドへ”」
From silver to "global standard gold"
現在、日本の平均寿命は男性81.0歳/女性87.1歳、10人に1人が80歳以上(2023年度)となり高齢化社会が年々加速しています。高齢者と定義される65歳以上の人口は総人口の29.3%(人口の約半分は50歳以上、平均寿命は49.9歳)を占め、世界第一位(200の国と地域)の長寿大国となりました。更には効率化を図るためのIT化や携帯電話・SNS等の普及によりデジタルとアナログが複雑に絡み合い、情報過多の時代へと急速に変化しつつあります。昔より生きづらくなったと感じる方も少なくないでしょう。
日本を取り巻く現状〜
現在、日本の平均寿命は男性81.0歳/女性87.1歳、10人に1人が80歳以上(2023年度)となり高齢化社会が年々加速しています。高齢者と定義される65歳以上の人口は総人口の29.3%(人口の約半分は50歳以上、平均寿命は49.9歳)を占め、世界第一位(200の国と地域)の長寿大国となりました。更には効率化を図るためのIT化や携帯電話・SNS等の普及によりデジタルとアナログが複雑に絡み合い、情報過多の時代へと急速に変化しつつあります。昔より生きづらくなったと感じる方も少なくないでしょう。
一方で、こういった時代においても現代の主役は若者ではなく間違いなくシニア世代の方々だと捉えています。だからこそ我々ゴールデン・イヤーズでは、このアナログの部分を大事にし、今までにない新しいカタチとして松戸市発の地域密着型コミュニティを作りました。
シルバーという言葉の起源・・・
日本では高齢者を指す言葉の一つに、「シルバー」という言葉があります。シルバー人材やシルバーシートなど、シルバーと名の付く高齢者用の言葉は多々あります。しかし、なぜ「シルバー」なのか?ホワイトなのではいけなかったのか?一度はそうした疑問を感じられた方も多いはずです。実は高齢者を意味するシルバーは和製英語。日本でたまたま誕生した言葉なのです。英語の「silver(銀)」とは別物。外国で高齢者をシルバーと呼んでも全く通用しません。仮に英語でシルバー人材(Silver Human Resources)と言っても、「銀色の人材」という意味で伝わってしまいます。下手すると変わったジョークだと勘違いされてしまうかもしれませんね。
シルバーの語源は1973年当時の国鉄(現在のJR)が初めて設置した高齢者優先席がシルバー“銀”であったことに由来しています。シルバー」という高齢者用の言葉が使われるようになったキッカケは、1973年9月15日の敬老の日まで遡ります。
当時の国鉄は赤字運営。敬老の日において高齢者のために、特別な優先席を設けることが決まりました。この優先席を一般席と区別するために、座席の色を変えようとしましたが、優先席専用の色を用意する時間もありませんでした。そこで国鉄は工場にたまたま在庫としてあった新幹線の座席カバーを使うことに。この座席カバーの色が「シルバー」だったことから、優先席は「シルバーシート」と呼ばれるようになったそうです。
このシルバーシートをきっかけに「シルバー=高齢者」のイメージが国民の間で徐々に定着化し、今では完全に浸透しています。まさか全国的にシルバーが高齢者だと認識されるとは、当時の国鉄も予想外だったことでしょう。高齢化が進んでいる日本だからこそ、シルバーという和製英語がここまで浸透したのかもしれませんね。